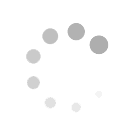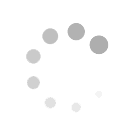後者は盤共に非常に状態の良い中古でございますが、ジャケットに若干使用感がございます。
前者は本国最新リマスター、後者は日本独自リマスターの模様でございます。
前者は現在主流の情報量重視で知られるフラットマスタリング方式によるものの模様。良心的な音質ではございます。
後者は日本独自リマスターでございますがオリジナルに即したもの、結構アナログ感が有り非常に良心的な音質となっております。
又、仕様もオリジナルに即した造りとなっております。
現在では今作含めこのPaul McCartney作品群最新リマスターがリリースされておりますが、作品によってはデータの音飛び等が指摘されております。
ファンを中心として指摘が為され、改善が求められておりますが、レーベル側は「これが正規」の一点張り。
(The Beatles某作品も同じ...................)
何をか言わんや、でございます.........................................
ラインナップは全盛期。
Paul McCartney(Vo、B、Aoustic G、Key ex-The Beatles)、故Linda McCartney(B-vo、Key、Per)、Denny Lane(G、Vo、Key、Per、Harmonica、ex-Moody Blues)、
故Jimmy McCullock(G、B、Vo、Per)、Joe English(Ds、Per、Vo)となります。
ツアー・ゲストに名手Howie Casey(Sax、Per)、Tony Dousey(Trombone、Per)、Steve Howard(Trumpet、Flugelhorn、Per)、Thaddeus Richard(Sax、Clarinet、Wester Concert Flute、Per)となります。
尚、Paul McCartneyがピアノを担当するDisc 1〈5〉~〈9〉、Disc 2〈1〉~〈5〉ではDenny Laneがベースを担当(”Go Now”除く)。
Paul McCartney/Denny Laneがアコースティック・ギターを担当するDisc 1〈10〉~〈15〉では故Jimmy McCullockがベースを担当。
”Richard Cory”、”Time to Hide”、御馴染み”Go Now”(ピアノ兼任。Paul McCartney自身はベース)、”Spirits of Ancient Egypt”では(パーカッション兼任)では、Denny Laneがヴォーカル担当。
”Medecine Jar”は故Jimmy McCullockのヴォーカル、となります。
プロデュースはPaul McCartney自身。
1976年5月7日~6月23日全米ツアーでの実況録音からの抜粋。
(実際は1976年6月23日米国カリフォルニア州”L.A.Forum”での実況録音が殆どの模様。
”Soily”は米国デンバー”McNichols Sports Arena”での実況録音となります(MCからも判断可能))
1976年10月~11月英国ロンドン”Abbey Road Studios”(オーヴァーダビング/音調整/ミキシング)となります。
”Band on the Run”制作直前に名手Henry McCullough/Denny Seiwellが突如脱退。
悲惨な制作環境と紆余曲折の末に残る三名による制作の”Band on the Run”が完成。リリース後は非常な好評とチャートアクション/セールスを叩き出します。
その後、オーディション選考を開始し、故Jimmy McCullockを獲得。
名手Gerry Conway(ex-Fairport Convention、Rupert Hineセッション他)のサポートを経て、Paul McCartney実弟”Mike McGear”の録音セッションに参加する事となります。
その後、Geoff Brittonを後任としてスカウト。新作制作に向け創作に乗り出していく事となります。
米国ルイジアナ州ニューオーリンズ”Sea-Saint Studios”にて録音制作を決定するも、その前に御馴染み”Abbey Road Studios”にて試験録音を行い、三曲を仮完成させます。
米国に移行し制作前にナッシュビルにて創作を兼ねたセッションを行うも、故Jimmy McCullochが新加入のGeoff Brittonとの感情的な対立を引き起こし、バンド内は険悪な雰囲気に。
Geoff Brittonは憤慨し急遽脱退。
その後のオーディション選考で米国人ドラマーJoe Englishを獲得。ニューオーリンズへ移行し新作制作に乗り出す事となります。
その新作”Venus and Mars”リリース後は前作に引き続き大ヒットを記録する事となります。
ようやく新体制にてライヴに臨む事となりますが、前作含めた作品の反響は非常に大きいもの。
Paul McCartney自身としてはThe Beatles以来となる大掛かりなツアーを企画、”Wings Over the World Tour”と銘打ち、実行に移す事となります。
されど、ツアーが企画され期待が高まる中、再び新作制作に乗り出す事となります........
再び二枚組企画で前作”Venus and Mars”を制作しようとしたもののレコード会社に拒否された感が有り、ロック色を強める為に外された楽曲を中心に再び新作制作に乗り出した感がございます。
(以前の”Red Rose Speedway”といい、後の”Tug of War””Pipes of Peace”の二作分けといい、Paul McCartneyには二枚組に絡む因縁が感じられるものでございます................)
Paul McCartney自身のみに注目が当たり、以前の”名手Henry McCullough脱退”の様な亀裂を避ける事、
以後のツアー活動での”Wings”のバンドとしての一体感を強める為という意図も制作に当たり伺えるものではございますが、短期間では仕上がらず制作を中断。
ツアーに乗り出す事となります。
スケジュール調整の末に英国/オーストラリア・ツアー~(幻の)日本公演後に再び制作に入る事が決定(.....以前の逮捕問題で日本入国が不可となった模様....後の大問題に繋がる事となりますが.........)、
新作制作完成に尽力する事となります......................
その”Wings at Speed of Sound”完成・リリース後は再び好評を以て迎えられ、バンドはヨーロッパそしてThe Beatles以来となる北米ツアーに乗り出します。
また当時は録音機器の非常な向上でライヴ録音の名盤が多く制作されていた事そしてバンドの演奏・アンサンブルの良さもあり、
伝説では無いリアルなロック・バンド”Paul McCartney & Wings”を体現する為に、ライヴ盤制作を前提としたライヴ録音収録に乗り出す事となります...........................
さて今作。
大傑作大ヒット2作”Band on the Run””Venus and Mars”を経て意欲作”Wings at Speed of Sound”を制作。
満を持して待望のツアーに乗り出した全盛期”Paul McCartney & Wings”のライヴ録音がミソでございます。
”Wings”はPaul McCartneyの音楽性体現の為のバンド。
Paul McCartney単体ではドラム/ギター演奏では技術的な問題があり、その解決や他ミュージシャンからの音楽的なインプットを欲した事を窺える感の有るものでございます。
如何にPaul McCartney自身の音楽性を発展させるか?を窺えるものでございます。
(この矛盾めいた感覚がメンバー交代に繋がる感も..........................)
されど、ここではライヴ。
バンドとしての演奏・アンサンブルが問題となりますが、チーム型名手ミュージシャンの集まりがミソ。
非常に纏まっており、ライヴ盤制作に意欲的に乗り出した事が理解出来るもの。
また、ライヴという事やギタリストが2名という事が有り、結構ハード感のあるものでございます。
当時英国では古典派アート・ロック系バンドがパンク/ニュー・ウェイヴに追い遣られるという時代。
されど、今作に絡む三作が大ヒットというこの”Wings”。未だその影響の強さを感じられるものでございます。
またPaul McCartney自身がベース以外の楽器を担当する事に代表される担当楽器交代が聴きもの。
当時はアート/ポピュラー系の名バンド”10㏄”が存在。
The Beatlesに繋がる音楽性が色濃く出た分裂後の時期でございますが、このバンドのライヴも担当楽器交代が結構見られるもの。
Paul McCartney自身は”10㏄”のルーツ的なミュージシャンとは言えど、参考にしていた感がございます。
Paul McCartneyがピアノ担当の際にDenny Laneがベースを担当となりますが、正直違和感ない出来。
Paul McCartneyのベース演奏はメロディ感覚が強いもの。
時代を切り開いたとも言われ、かのジャズ/フュージョン系にも影響を与えた感がございますが、基礎はギター演奏にある感。
(Paul McCartney自身は演奏者以前に基本は創作者。創作にはギターを主に用いた事に絡む感が.................................)
ギタリストが弾くベースという感が窺えるもので、ギタリストであるDenny Laneや故Jimmy McCullockの演奏に違和感が無い理由がここにある感がございます。
また前述の創作面含めたPaul McCartney主導のバンド”Wings”ではあるもののバンド形式を重視したいとのPaul McCartney本人の意向が有り、
Denny Laneや故Jimmy McCullockのリードヴォーカル楽曲をセットに多めに盛り込む等、興味深いものがございます。
かの名手故Henry McCulloughの脱退が余程堪えた感が窺えるものでございます....................................
またPaul McCartney自身が在籍したかの”The Beatles”やその後のソロ作からの選曲もミソ。
前者はかの”The Long and Widing Road”が「本来はこうしたかったヴァージョン」を基にしたもの。
またソロ楽曲では(録音当時の取り巻く状況が有り、本来は)バンドとしてこういう感じに仕上げたかったという感が感じられるもの。
非常に興味深いものがございます............................
(前者は後に”Let It be...Naked”で登場致しますが.........................
その”Let It Be..Naked”。
リリース当時は絶賛していたものの時間を経る内に記憶が甦り、非常に完成度は高いものの編集・仕上げ具合がPaul McCartney自身の考えと異なるものだった模様でございますが........................
当時の制作データ等に基づくものではございましたが..................................)
楽曲はメロディ重視で非常に質が高く、幅広い音楽性で飽きさせないもの。
されど案外趣味性が高いもので非常に凝ったもの。案外人を選ぶ感覚がある音楽性。
正直一般的なものではない事がミソでございます。
ライヴという事でシンプルさとハードさが強調された感がございますが、ツインギター体制でかなり躍動感がありロック色が強いものでございます。
後にバック・コーラスの録り直しを中心にオーヴァーダビングが為されておりますが、ライヴという範疇は踏み外していないもの。
そもそもライヴ録音は録音マイクの不調や音を拾っていない(興奮したドラマーはマイクを叩く等々...............)というアクシデントが伴うというもの。
ましてやロック音楽というもの(技術云々とは言えど、他分野曰くは...................................)。
ライヴという事でPaul McCartneyのピアノ・ミスやツイン・ギターのタイミングのズレ等々も敢えて残されており、記録より作品という色合いが強くなるライヴ盤ではございますが、
非常に出来が良く良心的でございます......................................
当時の英国古典派アート・ロック系に繋がる音楽性で当時の英国の風潮に逆らう感のあるものでございますが、次作制作極初期にて故Jimmy McCullochは制作の有り方に異議を唱え脱退。
全盛期ラインナップはあっけなく崩壊する事もあり、ライヴ盤ではございますが「Paul McCartneyソロ独立~Wings結成~全盛期」の纏め的な作品でもございます。
”The Beatles”人気が強く残っていた当時とは言えど、如何に当時の聴衆が鋭いものを求めていたか?が理解出来る内容でございます.......
ツアーが大好評に終わり、渇望されていたライヴ盤という事が有り、異例の三枚組リリースとなるものの大ヒット。
バンドは正に威風堂々。
されど前述のパンク/ニュー・ウェイヴの台頭を機に八十年代を見越し、ジャンルを超え新たな音楽性を模索し始めるという時期。
Paul McCartney自身はその中で新たな音楽性を模索し始める事となります...........................
されど、当時の日本入国不可問題に絡む「ミュージシャン特有の私生活問題」が故Jimmy McCullockを中心に深刻化していく事となり、創作面に悪影響を及ぼしていく事となります........................
また、前任名手故Henry McCullough脱退に絡むかの問題が再びバンドの頭を擡げてくる事となり、前述の問題と絡み、深刻化。
次作制作の有り方を巡り故Jimmy McCullockが制作極初期にて脱退。
全盛期があっけなく終焉を迎える事となります................................................
今作はライヴ盤の大傑作の一つに数えられる名作でございますが..................................
正直当時に日本公演が実現し、そこで録音に定評がある”Live in Japan”ライヴ録音が為されていれば.....................という感がございますが..............................
この機会に是非。