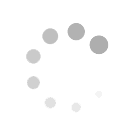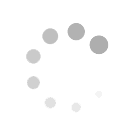google翻譯
Excite翻譯
google & Excite翻譯僅供參考,詳細問題說明請使用商品問與答
■岡長平 2011年発行 >